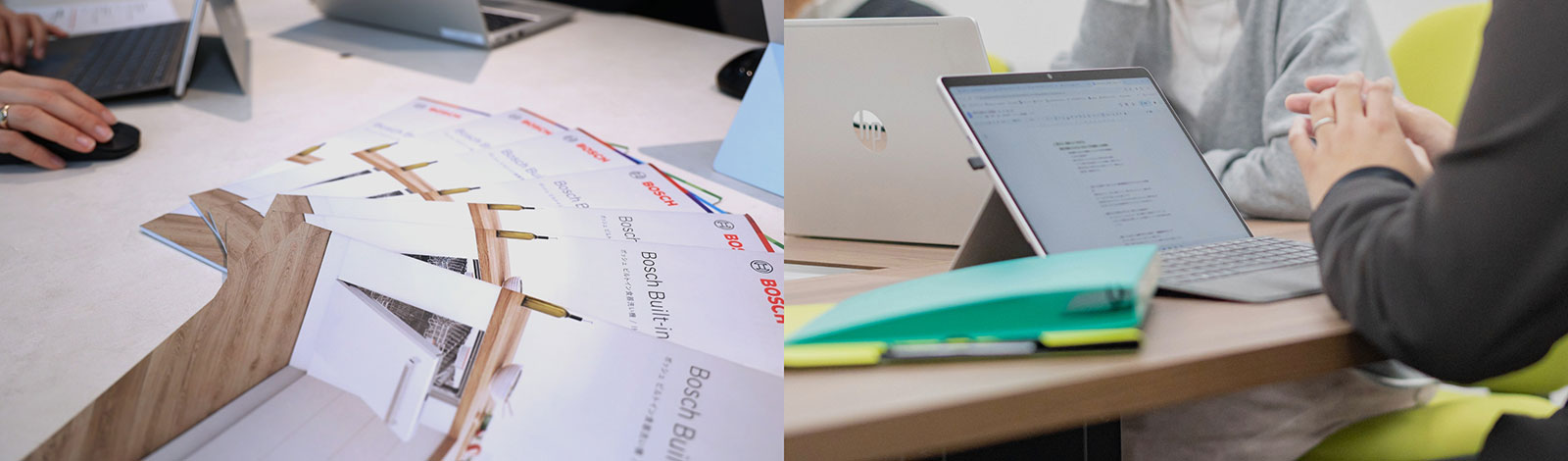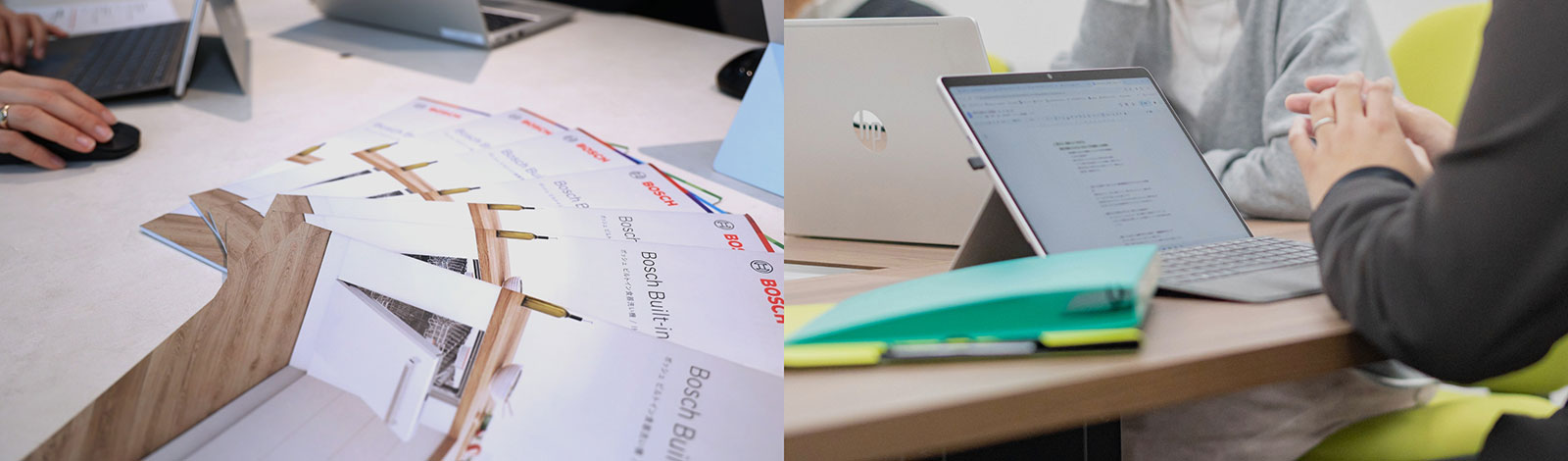代表メッセージ
『組織成果』について
仕事においては個⼈の成果と、それを⽣み出すための成⻑は不可⽋だと思います。ただし、個⼈の成果を1とした場合に、1+1=2ではなく、1+1を3以上にすることを可能にするのが、組織で活動する意味だと思います。そして、組織の中ではさまざまな分業も⾏われ、それが適材適所活⽤を⽣み出せる⼀⽅で、組織内でのセクショナリズムという弊害も⽣み出します。これには、個⼈のスキル向上や適材適所活⽤のメリットを打ち消すような負のパワーがあり、この弊害を⽣み出さないキーワードが「組織成果」にあると考えています。もちろん、この弊害もあるとは思いますが、私は全員が「組織成果」を重視できる会社になれば、将来の成⻑や今後⽣じる社会変化や課題への対応の原動⼒となると考えています。
勘違いをしないでいただきたいのは、組織に従順であることを求めているのではなく、⾃分が所属する組織の成果を最⼤化するために、どうすれば良いかを考えることを求めていて、その第⼀歩が、普段、共に仕事をする⼈たちとの、仕事上の連携・連動だと思っています。
『機能別組織』について
上記で組織成果について触れましたが、全メンバーの個人スキルや特性を最大限に活用するためには、組織が仕事上の機能(職務)で分業化されていて、その機能(職務)に適性のある人材が集まっている形が最適だと考えています。
当社では以前は営業チームの中に、いわゆる販売管理職(事務職)メンバーが所属していましたが、これを数年前に営業チームから切り離し、機能別組織化したことが大きな変化でした。一定規模以上の会社では、当たり前の組織形態だとは思いますが、人数が少なく、さまざまな兼任状態が生まれる中小企業である我々にとっては、大きな変化だったと思います。
そして、この考え方が次第に各グループやチームの運営にも適用され始めています。
ただし、この機能別組織化の最大のネックはセクショナリズムであり、これを起こしにくくするための考え方が先ほど話した「組織成果」という考え方の浸透だと考えています。
このセクショナリズムを起こさないために、当社では『仕事上の各機能の重要性に優劣はない』と明言しており、ただし、仕事の流れ上の順序(例えば、商品開発→営業→受発注→経理処理など)はあると説明しています。そして、それぞれがこの流れの前後の仕事上の機能を理解して、連動することが重要だと考えています。つまり、どこかの部署の仕事だけが最適化されていても、その結果として他の部署の活動効率が落ちていれば、そこがボトルネックとなり全体の成果はそこへ収斂されたり、大きな課題になったりすることを意識する必要があるということです。